はじめに
アパレルやフットウェアを取り扱うファッションブランドやEC事業者にとって、オンラインで適切なサイズを伝えることは長年の課題です。
サイズへの不安から購入をためらうユーザー、返品を前提に商品を注文するユーザー、そして結果として発生する高い返品率——これらはすべて、購入前に「この商品のサイズは自分に合うだろうか?」という疑問が解消されないことに起因しています。
実際、アパレルECにおけるグローバル平均の返品率は26%。そのうち50%以上が「サイズやフィット感の不一致」が原因とされています。
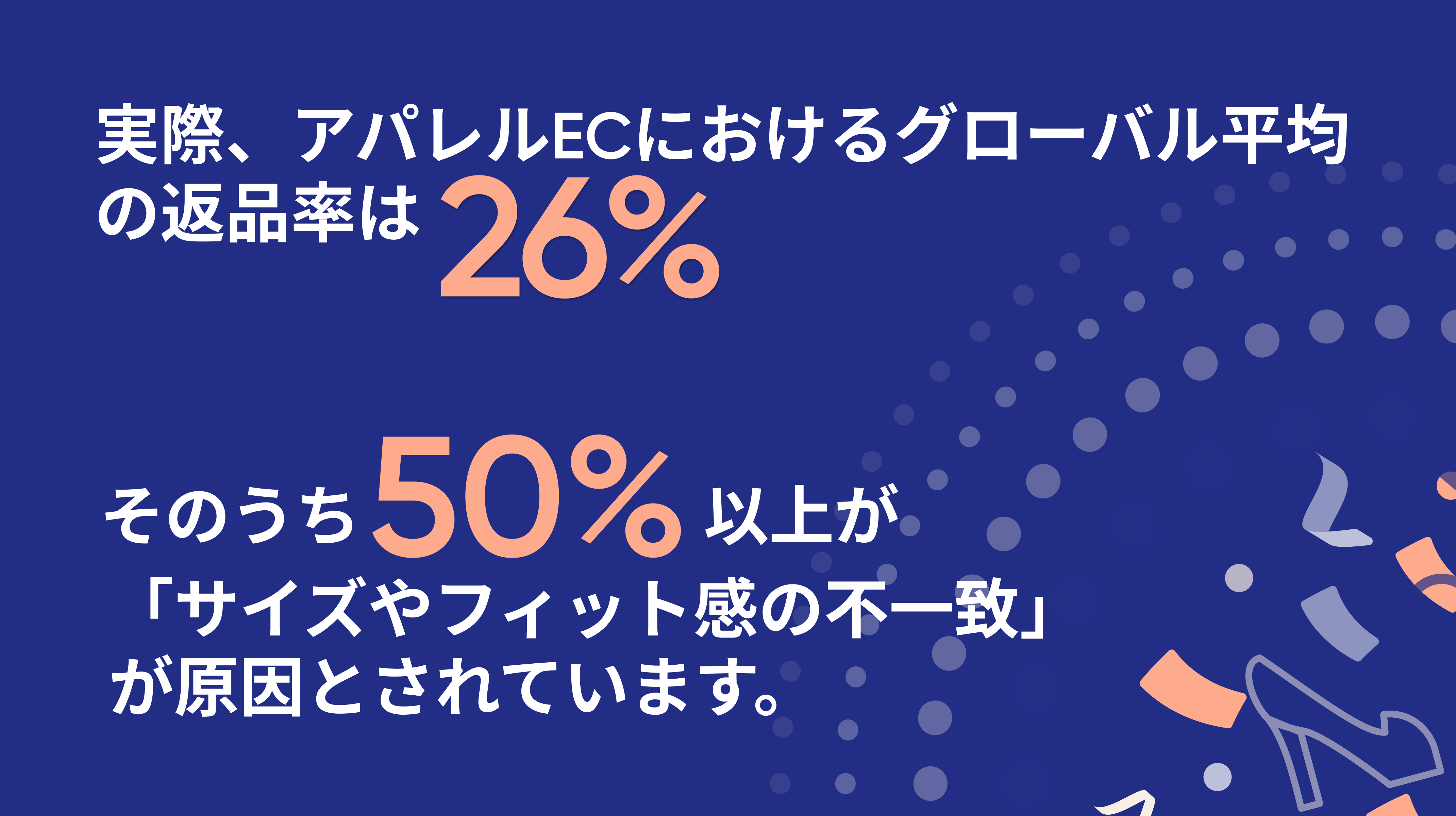
こうした背景を受けて、いま多くのブランドが「バーチャルフィッティング(試着)ソリューション」の導入に注目しています。
バーチャルフィッティングとは?
バーチャルフィッティングとは、オンラインショッピングで自分に合うサイズを選ぶのに役立つデジタルソリューションです。
店舗で実際に試着する体験に近づけることでサイズへの不安を解消し、購入意欲を高めることが目的です。
「バーチャル試着」「サイズ比較」「サイズシミュレーション」など、さまざまな言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、以下のように整理できます。
● バーチャル/オンラインフィッティング:オンライン上で商品のフィット感を確認する技術全般
● バーチャル/オンライン試着:ユーザーの身体(実写やアバター)に服を視覚的に重ねて表示する技術
○ 3D/AR試着:カメラやAR(拡張現実)技術を使って、実際の身体に服を重ねて表示する技術(サイズを知るというよりは、見た目の確認に重点が置かれます)
● サイズレコメンドツール:商品情報とユーザー入力データを元に最適なサイズを提案する技術
なぜ2025年の今導入すべきか
バーチャルフィッティングソリューションは、ファッションECにおいて「あると便利」なものから「必要不可欠なもの」へと進化しています。
● デジタルネイティブの期待値
Z世代を中心とした若い購買層は、スムーズな購入体験や高精度なパーソナライズを当然と考えています。
SNSや他のアプリでの体験に慣れている彼らにとって、旧来型の「サイズ表だけ」のUXでは満足度が低くなります。
● AIによる進化とコストの低下
AIと機械学習技術の進化により、より正確かつ手頃になり、1年前と比べてもはるかに多くのことが可能になっています。
● オムニチャネル対応の必須化
ラグジュアリーブランドであってもスポーツブランドであっても、オンラインとオフライン両方で一貫した顧客体験が求められています。
「実店舗と同じレベルの提案力をオンラインでも」——バーチャルフィッティングはその鍵となります。
● サステナビリティの新しい選択肢
バーチャルフィッティングの導入による返品削減は、ブランドの環境目標(ESG)の達成に向けた、取り組みやすいアクションです。
バーチャルフィッティングが解決する課題
ユーザーが「自分に合うかわからない」と感じた時点で、購入は止まりがちです。
多くの場合、購入そのものをあきらめるか、返品前提での購入に切り替わってしまいます。
返品ポリシーが厳しければ購入には至らず、購入体験そのものが不満の残るものになってしまいます。
この問題を解消することで、返品率の削減はもちろん、UXや売上にも良い影響を与えます。
- 短期的な効果
● 返品率の削減
サイズ選択ミスが少なければ、それだけ返品件数も減少します。たとえばUnder Armourでは、Virtusize導入後、サイズ関連の返品が前年比で27%削減され、サステナビリティ目標にも良い影響を与えました。
● コンバージョン率の向上
購入直前の迷いを取り除くことで、より多くのユーザーが購入に踏み切ることができます。Asicsでは、Virtusizeを利用したユーザーのコンバージョン率(CVR)が、非利用ユーザーと比べて10.5倍に。
● AOV(平均注文額)の上昇
サイズに対する安心感が高まると、まとめ買いやアップセルにつながります。
● サステナビリティの促進
返品の削減は配送・パッケージ資材・倉庫処理コストの削減につながり、環境負荷の低減にも貢献します。
- 長期的な効果
● ユーザー体験とブランドロイヤルティの向上
スムーズな購買体験は顧客満足度を高め、LTV(顧客生涯価値)を伸ばし、定着率向上にもつながります。
● データ活用の拡張
ユーザーの体型やサイズ選びの傾向は、商品開発・在庫計画・マーケティングに活用できる貴重な情報です。
● オペレーション効率の改善
返品処理・カスタマーサポートの負荷が減少し、チームの時間を高付加価値な業務に振り向けられます。
最適なバーチャルフィッティングソリューションの選び方
すべてのバーチャル試着ツールが同じように作られ、同じように動作するわけではありません。ブランドやECプラットフォームに最適なソリューションは、達成したい目標、必要な柔軟性、ビジネスの規模や複雑性によって異なります。以下に、試着ソリューションを比較する際のポイントをご紹介します。
- 目標を明確にする
●まずは、改善したい指標を明確にしましょう。
返品率の削減、コンバージョン率の向上、ユーザー体験の改善、リピーターの獲得など
●自社ECサイトの課題を洗い出しましょう。
UXフローに問題がある、サイズ情報がわかりにくい、選択肢が多すぎて購入判断に影響している、など
● これらの課題を解決するために、どれだけの費用や時間をかける価値があるかを明確にしましょう。
- 自社サイトにとって現実的な選択肢かを見極める
すべてのフィッティングソリューションが、あらゆるビジネスに適しているわけではありません。中小規模のブランドにとっては、高額な固定費や大企業向けの構成が原因で、ツールが複雑かつ高額になる可能性があります。
たとえば、小規模で高品質の商品を扱うブランドであれば、「プレミアム感」を維持するためにカスタマイズ性やブランディングを重視しつつ、利用量に応じた従量課金制の価格プランを検討するのが適しているかもしれません。
既存システムへの導入のしやすさ(手動入力と自動入力のバランス)も重要な要素です。以下のような点を確認しましょう。
・価格モデルは従量課金型、固定料金型、またはその混合型か?
・初期設定費用はかかるか?
・価格は今後の事業成長に合わせて適切に設定されているか?
・実装に必要な要件は?
・必要な採寸データを保有しているか?
・導入効果を測定するための指標を確認できるか?
- ユーザー体験を最優先に
多くのツールが、操作が複雑だったり、反応が遅かったり、買い物体験とうまく合っていなかったりします。
ユーザー体験を損なわない以下のようなソリューションを選びましょう。
・ 最小限のクリックで完了
・ 商品詳細ページに直接実装可能
・ 自社ブランドに合ったデザインカスタマイズが可能
「オンラインショッピングでは、自信がすべてです。とくにサイズ選びではなおさらです。体験がもたついたり、長すぎたり、分かりにくかったりすると、ユーザーの信頼はすぐに失われます。」
— 高木エモリー(Virtusize デザイン責任者)
- 本当にデータモデリングを活用しているか、それともただの“AI風”か?
一部のソリューションは、汎用的なサイズ表や見せかけの「AI」に依存しており、実際の精度向上にはつながっていないケースがあります。
ソリューションを評価する際には、以下の点を確認しましょう。
・サイズレコメンドは、実際のデータモデリングに基づいているか?
・それとも、単純なロジックや「AI」という言葉だけを使っているに過ぎないか?
「“AI”という言葉を使うのは簡単ですが、重要なのは、そのシステムが服や身体を本当に理解しているかどうかです。本当の効果は、実データに基づいて個別に構築されたレコメンドロジックから生まれます。Virtusizeのデータサイエンスチームは、それぞれのブランドとユーザーに最適化されたロジックを構築・調整しています。」
— アーロン・リッチー(Virtusize データサイエンス責任者)
バーチャルフィッティングソリューションの選定は、単なる機能比較ではありません。
ブランドの成長戦略、技術的なニーズ、ユーザー体験に対する価値観を総合的に考慮し、将来を見据えた選択が重要です。
今後のために、押さえておくべきポイント
● AIによる超高精度フィッティング
機械学習モデルの進化により、少ないデータ入力でもより精度が高く、よりパーソナライズされたサイズレコメンドが可能になってきています。Virtusizeでは、性別・身長・体重・年齢の4つの入力だけでパーソナライズされたレコメンドを実現しています。
● サイズデータの社内活用
いまやバーチャルフィッティングは、ユーザーのためだけでなく、ブランドの意思決定にも使われています。得られる体型データはさまざまなことに活用が可能です。
○ 購買行動や性別、地域に「体型」や「フィットの好み」といった視点を加えることで、より正確で深い顧客理解が可能に
○商品企画や生産計画に活用することで、新商品の設計や販売数の予測精度も高まります
● テクノロジーの進化
近い将来、チャットや音声だけでショッピングが完結するようになるでしょう。TikTokなどのSNSでも、コンテンツからそのまま買い物ができる体験が広がっており、どのチャネルでもパーソナライズされた体験が「当たり前」になっていきます。
そのとき、サイズやフィットに関するデータがあることで、お客様がスムーズに商品を見つけ、安心して購入につながる。これは、今後の収益機会を広げるためにも非常に重要な要素になります。
まとめ:今こそ「サイズ課題」に取り組むべき理由
サイズやフィットに関する課題は、ファッションECにおける最大の障壁のひとつです。売上機会の損失、返品率の上昇、顧客満足度の低下など、さまざまな悪影響を及ぼしています。
こうした課題に対し、バーチャルフィッティングソリューションは明確な解決策を提示してくれます。購入率の向上、返品率の削減、そしてサステナビリティ目標への貢献——すべてを同時に実現できる可能性があります。
このテクノロジーはすでに実用段階にあり、十分な成果を出せる水準に達しています。AIやデータモデリングを活用した最新ツールでは、最小限の入力だけで高精度なサイズレコメンドが可能になっており、今まさに活用を検討する絶好のタイミングです。
ただし、成果を上げるためには、自社のブランドやビジネスニーズに本当に合ったソリューションを選ぶことが重要です。何を目指しているのか、どれだけのリソースを投下できるのか、そして何より「お客様が求めていることは何か」。こうした視点が欠かせません。
自社の課題とゴールに合致したソリューションを選定し、サイズ課題をビジネス成長の武器に変えましょう。
→ Under ArmourやAsicsの事例を見る(返品27%削減/ CVR10倍)
→ Virtusizeのデモをリクエストする(お問い合わせはこちら)
はじめに
アパレルやフットウェアを取り扱うファッションブランドやEC事業者にとって、オンラインで適切なサイズを伝えることは長年の課題です。
サイズへの不安から購入をためらうユーザー、返品を前提に商品を注文するユーザー、そして結果として発生する高い返品率——これらはすべて、購入前に「この商品のサイズは自分に合うだろうか?」という疑問が解消されないことに起因しています。
実際、アパレルECにおけるグローバル平均の返品率は26%。そのうち50%以上が「サイズやフィット感の不一致」が原因とされています。
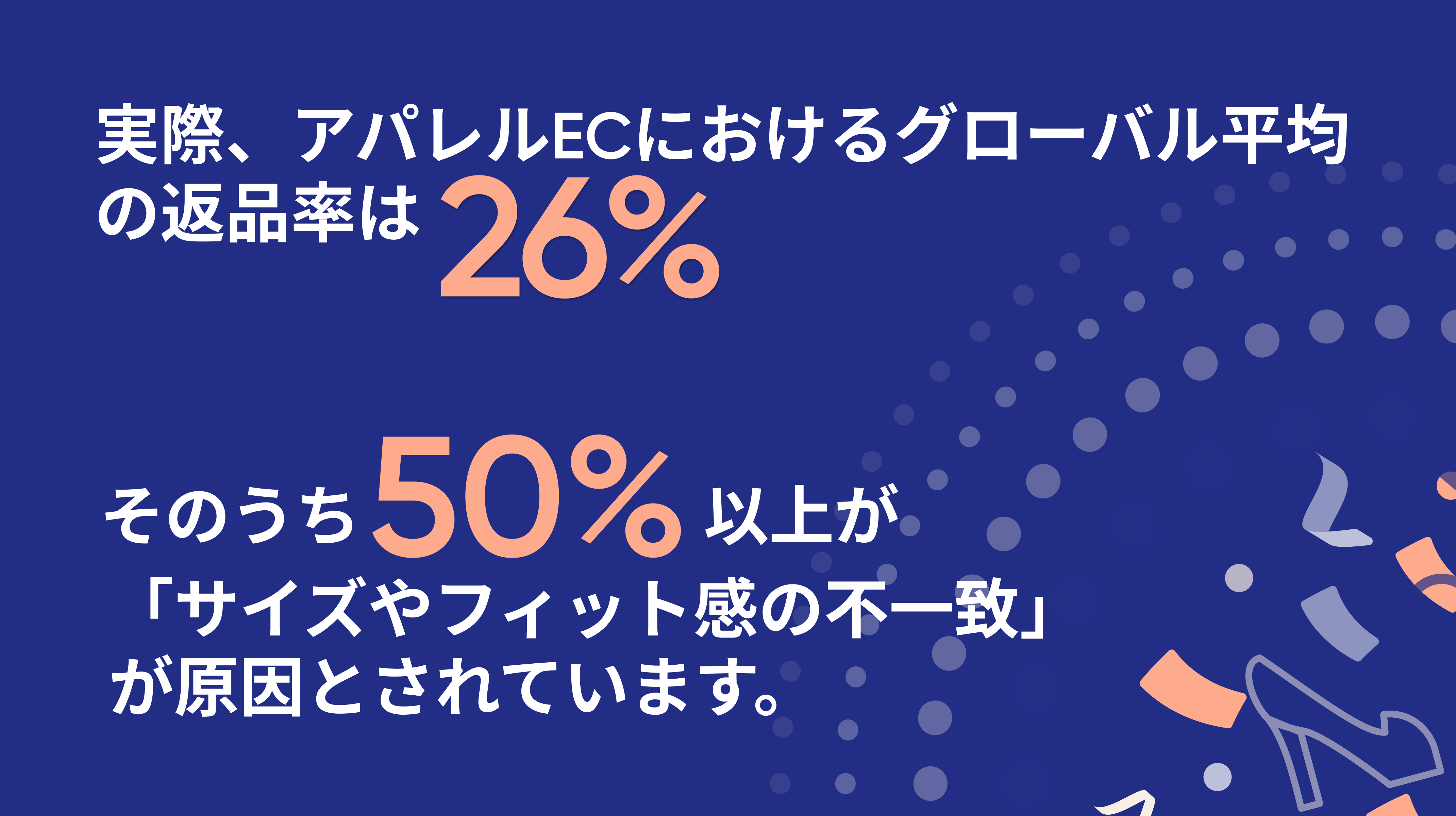
こうした背景を受けて、いま多くのブランドが「バーチャルフィッティング(試着)ソリューション」の導入に注目しています。
バーチャルフィッティングとは?
バーチャルフィッティングとは、オンラインショッピングで自分に合うサイズを選ぶのに役立つデジタルソリューションです。
店舗で実際に試着する体験に近づけることでサイズへの不安を解消し、購入意欲を高めることが目的です。
「バーチャル試着」「サイズ比較」「サイズシミュレーション」など、さまざまな言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、以下のように整理できます。
● バーチャル/オンラインフィッティング:オンライン上で商品のフィット感を確認する技術全般
● バーチャル/オンライン試着:ユーザーの身体(実写やアバター)に服を視覚的に重ねて表示する技術
○ 3D/AR試着:カメラやAR(拡張現実)技術を使って、実際の身体に服を重ねて表示する技術(サイズを知るというよりは、見た目の確認に重点が置かれます)
● サイズレコメンドツール:商品情報とユーザー入力データを元に最適なサイズを提案する技術
なぜ2025年の今導入すべきか
バーチャルフィッティングソリューションは、ファッションECにおいて「あると便利」なものから「必要不可欠なもの」へと進化しています。
● デジタルネイティブの期待値
Z世代を中心とした若い購買層は、スムーズな購入体験や高精度なパーソナライズを当然と考えています。
SNSや他のアプリでの体験に慣れている彼らにとって、旧来型の「サイズ表だけ」のUXでは満足度が低くなります。
● AIによる進化とコストの低下
AIと機械学習技術の進化により、より正確かつ手頃になり、1年前と比べてもはるかに多くのことが可能になっています。
● オムニチャネル対応の必須化
ラグジュアリーブランドであってもスポーツブランドであっても、オンラインとオフライン両方で一貫した顧客体験が求められています。
「実店舗と同じレベルの提案力をオンラインでも」——バーチャルフィッティングはその鍵となります。
● サステナビリティの新しい選択肢
バーチャルフィッティングの導入による返品削減は、ブランドの環境目標(ESG)の達成に向けた、取り組みやすいアクションです。
バーチャルフィッティングが解決する課題
ユーザーが「自分に合うかわからない」と感じた時点で、購入は止まりがちです。
多くの場合、購入そのものをあきらめるか、返品前提での購入に切り替わってしまいます。
返品ポリシーが厳しければ購入には至らず、購入体験そのものが不満の残るものになってしまいます。
この問題を解消することで、返品率の削減はもちろん、UXや売上にも良い影響を与えます。
- 短期的な効果
● 返品率の削減
サイズ選択ミスが少なければ、それだけ返品件数も減少します。たとえばUnder Armourでは、Virtusize導入後、サイズ関連の返品が前年比で27%削減され、サステナビリティ目標にも良い影響を与えました。
● コンバージョン率の向上
購入直前の迷いを取り除くことで、より多くのユーザーが購入に踏み切ることができます。Asicsでは、Virtusizeを利用したユーザーのコンバージョン率(CVR)が、非利用ユーザーと比べて10.5倍に。
● AOV(平均注文額)の上昇
サイズに対する安心感が高まると、まとめ買いやアップセルにつながります。
● サステナビリティの促進
返品の削減は配送・パッケージ資材・倉庫処理コストの削減につながり、環境負荷の低減にも貢献します。
- 長期的な効果
● ユーザー体験とブランドロイヤルティの向上
スムーズな購買体験は顧客満足度を高め、LTV(顧客生涯価値)を伸ばし、定着率向上にもつながります。
● データ活用の拡張
ユーザーの体型やサイズ選びの傾向は、商品開発・在庫計画・マーケティングに活用できる貴重な情報です。
● オペレーション効率の改善
返品処理・カスタマーサポートの負荷が減少し、チームの時間を高付加価値な業務に振り向けられます。
最適なバーチャルフィッティングソリューションの選び方
すべてのバーチャル試着ツールが同じように作られ、同じように動作するわけではありません。ブランドやECプラットフォームに最適なソリューションは、達成したい目標、必要な柔軟性、ビジネスの規模や複雑性によって異なります。以下に、試着ソリューションを比較する際のポイントをご紹介します。
- 目標を明確にする
●まずは、改善したい指標を明確にしましょう。
返品率の削減、コンバージョン率の向上、ユーザー体験の改善、リピーターの獲得など
●自社ECサイトの課題を洗い出しましょう。
UXフローに問題がある、サイズ情報がわかりにくい、選択肢が多すぎて購入判断に影響している、など
● これらの課題を解決するために、どれだけの費用や時間をかける価値があるかを明確にしましょう。
- 自社サイトにとって現実的な選択肢かを見極める
すべてのフィッティングソリューションが、あらゆるビジネスに適しているわけではありません。中小規模のブランドにとっては、高額な固定費や大企業向けの構成が原因で、ツールが複雑かつ高額になる可能性があります。
たとえば、小規模で高品質の商品を扱うブランドであれば、「プレミアム感」を維持するためにカスタマイズ性やブランディングを重視しつつ、利用量に応じた従量課金制の価格プランを検討するのが適しているかもしれません。
既存システムへの導入のしやすさ(手動入力と自動入力のバランス)も重要な要素です。以下のような点を確認しましょう。
・価格モデルは従量課金型、固定料金型、またはその混合型か?
・初期設定費用はかかるか?
・価格は今後の事業成長に合わせて適切に設定されているか?
・実装に必要な要件は?
・必要な採寸データを保有しているか?
・導入効果を測定するための指標を確認できるか?
- ユーザー体験を最優先に
多くのツールが、操作が複雑だったり、反応が遅かったり、買い物体験とうまく合っていなかったりします。
ユーザー体験を損なわない以下のようなソリューションを選びましょう。
・ 最小限のクリックで完了
・ 商品詳細ページに直接実装可能
・ 自社ブランドに合ったデザインカスタマイズが可能
「オンラインショッピングでは、自信がすべてです。とくにサイズ選びではなおさらです。体験がもたついたり、長すぎたり、分かりにくかったりすると、ユーザーの信頼はすぐに失われます。」
— 高木エモリー(Virtusize デザイン責任者)
- 本当にデータモデリングを活用しているか、それともただの“AI風”か?
一部のソリューションは、汎用的なサイズ表や見せかけの「AI」に依存しており、実際の精度向上にはつながっていないケースがあります。
ソリューションを評価する際には、以下の点を確認しましょう。
・サイズレコメンドは、実際のデータモデリングに基づいているか?
・それとも、単純なロジックや「AI」という言葉だけを使っているに過ぎないか?
「“AI”という言葉を使うのは簡単ですが、重要なのは、そのシステムが服や身体を本当に理解しているかどうかです。本当の効果は、実データに基づいて個別に構築されたレコメンドロジックから生まれます。Virtusizeのデータサイエンスチームは、それぞれのブランドとユーザーに最適化されたロジックを構築・調整しています。」
— アーロン・リッチー(Virtusize データサイエンス責任者)
バーチャルフィッティングソリューションの選定は、単なる機能比較ではありません。
ブランドの成長戦略、技術的なニーズ、ユーザー体験に対する価値観を総合的に考慮し、将来を見据えた選択が重要です。
今後のために、押さえておくべきポイント
● AIによる超高精度フィッティング
機械学習モデルの進化により、少ないデータ入力でもより精度が高く、よりパーソナライズされたサイズレコメンドが可能になってきています。Virtusizeでは、性別・身長・体重・年齢の4つの入力だけでパーソナライズされたレコメンドを実現しています。
● サイズデータの社内活用
いまやバーチャルフィッティングは、ユーザーのためだけでなく、ブランドの意思決定にも使われています。得られる体型データはさまざまなことに活用が可能です。
○ 購買行動や性別、地域に「体型」や「フィットの好み」といった視点を加えることで、より正確で深い顧客理解が可能に
○商品企画や生産計画に活用することで、新商品の設計や販売数の予測精度も高まります
● テクノロジーの進化
近い将来、チャットや音声だけでショッピングが完結するようになるでしょう。TikTokなどのSNSでも、コンテンツからそのまま買い物ができる体験が広がっており、どのチャネルでもパーソナライズされた体験が「当たり前」になっていきます。
そのとき、サイズやフィットに関するデータがあることで、お客様がスムーズに商品を見つけ、安心して購入につながる。これは、今後の収益機会を広げるためにも非常に重要な要素になります。
まとめ:今こそ「サイズ課題」に取り組むべき理由
サイズやフィットに関する課題は、ファッションECにおける最大の障壁のひとつです。売上機会の損失、返品率の上昇、顧客満足度の低下など、さまざまな悪影響を及ぼしています。
こうした課題に対し、バーチャルフィッティングソリューションは明確な解決策を提示してくれます。購入率の向上、返品率の削減、そしてサステナビリティ目標への貢献——すべてを同時に実現できる可能性があります。
このテクノロジーはすでに実用段階にあり、十分な成果を出せる水準に達しています。AIやデータモデリングを活用した最新ツールでは、最小限の入力だけで高精度なサイズレコメンドが可能になっており、今まさに活用を検討する絶好のタイミングです。
ただし、成果を上げるためには、自社のブランドやビジネスニーズに本当に合ったソリューションを選ぶことが重要です。何を目指しているのか、どれだけのリソースを投下できるのか、そして何より「お客様が求めていることは何か」。こうした視点が欠かせません。
自社の課題とゴールに合致したソリューションを選定し、サイズ課題をビジネス成長の武器に変えましょう。
→ Under ArmourやAsicsの事例を見る(返品27%削減/ CVR10倍)
→ Virtusizeのデモをリクエストする(お問い合わせはこちら)
はじめに
アパレルやフットウェアを取り扱うファッションブランドやEC事業者にとって、オンラインで適切なサイズを伝えることは長年の課題です。
サイズへの不安から購入をためらうユーザー、返品を前提に商品を注文するユーザー、そして結果として発生する高い返品率——これらはすべて、購入前に「この商品のサイズは自分に合うだろうか?」という疑問が解消されないことに起因しています。
実際、アパレルECにおけるグローバル平均の返品率は26%。そのうち50%以上が「サイズやフィット感の不一致」が原因とされています。
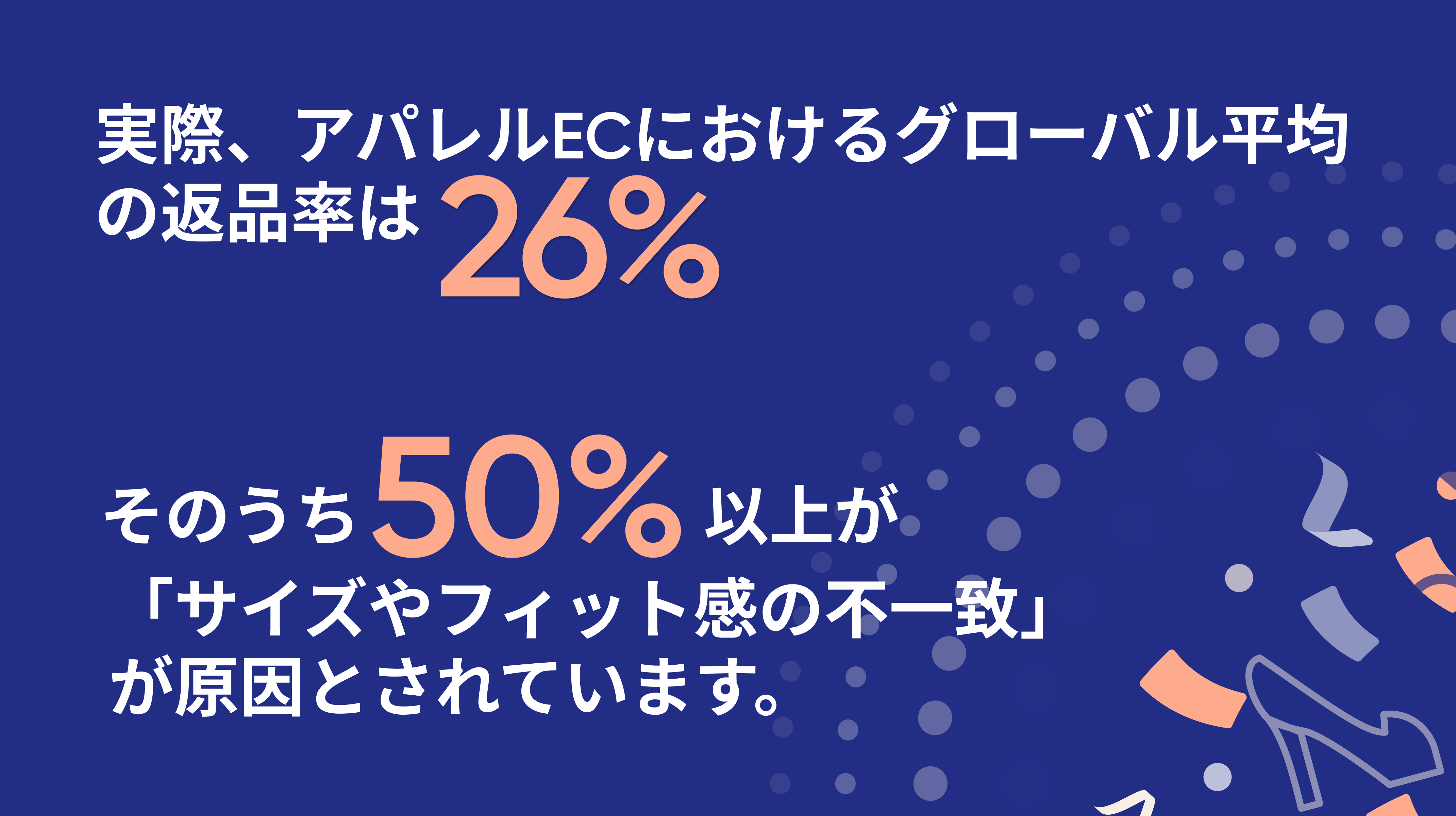
こうした背景を受けて、いま多くのブランドが「バーチャルフィッティング(試着)ソリューション」の導入に注目しています。
バーチャルフィッティングとは?
バーチャルフィッティングとは、オンラインショッピングで自分に合うサイズを選ぶのに役立つデジタルソリューションです。
店舗で実際に試着する体験に近づけることでサイズへの不安を解消し、購入意欲を高めることが目的です。
「バーチャル試着」「サイズ比較」「サイズシミュレーション」など、さまざまな言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、以下のように整理できます。
● バーチャル/オンラインフィッティング:オンライン上で商品のフィット感を確認する技術全般
● バーチャル/オンライン試着:ユーザーの身体(実写やアバター)に服を視覚的に重ねて表示する技術
○ 3D/AR試着:カメラやAR(拡張現実)技術を使って、実際の身体に服を重ねて表示する技術(サイズを知るというよりは、見た目の確認に重点が置かれます)
● サイズレコメンドツール:商品情報とユーザー入力データを元に最適なサイズを提案する技術
なぜ2025年の今導入すべきか
バーチャルフィッティングソリューションは、ファッションECにおいて「あると便利」なものから「必要不可欠なもの」へと進化しています。
● デジタルネイティブの期待値
Z世代を中心とした若い購買層は、スムーズな購入体験や高精度なパーソナライズを当然と考えています。
SNSや他のアプリでの体験に慣れている彼らにとって、旧来型の「サイズ表だけ」のUXでは満足度が低くなります。
● AIによる進化とコストの低下
AIと機械学習技術の進化により、より正確かつ手頃になり、1年前と比べてもはるかに多くのことが可能になっています。
● オムニチャネル対応の必須化
ラグジュアリーブランドであってもスポーツブランドであっても、オンラインとオフライン両方で一貫した顧客体験が求められています。
「実店舗と同じレベルの提案力をオンラインでも」——バーチャルフィッティングはその鍵となります。
● サステナビリティの新しい選択肢
バーチャルフィッティングの導入による返品削減は、ブランドの環境目標(ESG)の達成に向けた、取り組みやすいアクションです。
バーチャルフィッティングが解決する課題
ユーザーが「自分に合うかわからない」と感じた時点で、購入は止まりがちです。
多くの場合、購入そのものをあきらめるか、返品前提での購入に切り替わってしまいます。
返品ポリシーが厳しければ購入には至らず、購入体験そのものが不満の残るものになってしまいます。
この問題を解消することで、返品率の削減はもちろん、UXや売上にも良い影響を与えます。
- 短期的な効果
● 返品率の削減
サイズ選択ミスが少なければ、それだけ返品件数も減少します。たとえばUnder Armourでは、Virtusize導入後、サイズ関連の返品が前年比で27%削減され、サステナビリティ目標にも良い影響を与えました。
● コンバージョン率の向上
購入直前の迷いを取り除くことで、より多くのユーザーが購入に踏み切ることができます。Asicsでは、Virtusizeを利用したユーザーのコンバージョン率(CVR)が、非利用ユーザーと比べて10.5倍に。
● AOV(平均注文額)の上昇
サイズに対する安心感が高まると、まとめ買いやアップセルにつながります。
● サステナビリティの促進
返品の削減は配送・パッケージ資材・倉庫処理コストの削減につながり、環境負荷の低減にも貢献します。
- 長期的な効果
● ユーザー体験とブランドロイヤルティの向上
スムーズな購買体験は顧客満足度を高め、LTV(顧客生涯価値)を伸ばし、定着率向上にもつながります。
● データ活用の拡張
ユーザーの体型やサイズ選びの傾向は、商品開発・在庫計画・マーケティングに活用できる貴重な情報です。
● オペレーション効率の改善
返品処理・カスタマーサポートの負荷が減少し、チームの時間を高付加価値な業務に振り向けられます。
最適なバーチャルフィッティングソリューションの選び方
すべてのバーチャル試着ツールが同じように作られ、同じように動作するわけではありません。ブランドやECプラットフォームに最適なソリューションは、達成したい目標、必要な柔軟性、ビジネスの規模や複雑性によって異なります。以下に、試着ソリューションを比較する際のポイントをご紹介します。
- 目標を明確にする
●まずは、改善したい指標を明確にしましょう。
返品率の削減、コンバージョン率の向上、ユーザー体験の改善、リピーターの獲得など
●自社ECサイトの課題を洗い出しましょう。
UXフローに問題がある、サイズ情報がわかりにくい、選択肢が多すぎて購入判断に影響している、など
● これらの課題を解決するために、どれだけの費用や時間をかける価値があるかを明確にしましょう。
- 自社サイトにとって現実的な選択肢かを見極める
すべてのフィッティングソリューションが、あらゆるビジネスに適しているわけではありません。中小規模のブランドにとっては、高額な固定費や大企業向けの構成が原因で、ツールが複雑かつ高額になる可能性があります。
たとえば、小規模で高品質の商品を扱うブランドであれば、「プレミアム感」を維持するためにカスタマイズ性やブランディングを重視しつつ、利用量に応じた従量課金制の価格プランを検討するのが適しているかもしれません。
既存システムへの導入のしやすさ(手動入力と自動入力のバランス)も重要な要素です。以下のような点を確認しましょう。
・価格モデルは従量課金型、固定料金型、またはその混合型か?
・初期設定費用はかかるか?
・価格は今後の事業成長に合わせて適切に設定されているか?
・実装に必要な要件は?
・必要な採寸データを保有しているか?
・導入効果を測定するための指標を確認できるか?
- ユーザー体験を最優先に
多くのツールが、操作が複雑だったり、反応が遅かったり、買い物体験とうまく合っていなかったりします。
ユーザー体験を損なわない以下のようなソリューションを選びましょう。
・ 最小限のクリックで完了
・ 商品詳細ページに直接実装可能
・ 自社ブランドに合ったデザインカスタマイズが可能
「オンラインショッピングでは、自信がすべてです。とくにサイズ選びではなおさらです。体験がもたついたり、長すぎたり、分かりにくかったりすると、ユーザーの信頼はすぐに失われます。」
— 高木エモリー(Virtusize デザイン責任者)
- 本当にデータモデリングを活用しているか、それともただの“AI風”か?
一部のソリューションは、汎用的なサイズ表や見せかけの「AI」に依存しており、実際の精度向上にはつながっていないケースがあります。
ソリューションを評価する際には、以下の点を確認しましょう。
・サイズレコメンドは、実際のデータモデリングに基づいているか?
・それとも、単純なロジックや「AI」という言葉だけを使っているに過ぎないか?
「“AI”という言葉を使うのは簡単ですが、重要なのは、そのシステムが服や身体を本当に理解しているかどうかです。本当の効果は、実データに基づいて個別に構築されたレコメンドロジックから生まれます。Virtusizeのデータサイエンスチームは、それぞれのブランドとユーザーに最適化されたロジックを構築・調整しています。」
— アーロン・リッチー(Virtusize データサイエンス責任者)
バーチャルフィッティングソリューションの選定は、単なる機能比較ではありません。
ブランドの成長戦略、技術的なニーズ、ユーザー体験に対する価値観を総合的に考慮し、将来を見据えた選択が重要です。
今後のために、押さえておくべきポイント
● AIによる超高精度フィッティング
機械学習モデルの進化により、少ないデータ入力でもより精度が高く、よりパーソナライズされたサイズレコメンドが可能になってきています。Virtusizeでは、性別・身長・体重・年齢の4つの入力だけでパーソナライズされたレコメンドを実現しています。
● サイズデータの社内活用
いまやバーチャルフィッティングは、ユーザーのためだけでなく、ブランドの意思決定にも使われています。得られる体型データはさまざまなことに活用が可能です。
○ 購買行動や性別、地域に「体型」や「フィットの好み」といった視点を加えることで、より正確で深い顧客理解が可能に
○商品企画や生産計画に活用することで、新商品の設計や販売数の予測精度も高まります
● テクノロジーの進化
近い将来、チャットや音声だけでショッピングが完結するようになるでしょう。TikTokなどのSNSでも、コンテンツからそのまま買い物ができる体験が広がっており、どのチャネルでもパーソナライズされた体験が「当たり前」になっていきます。
そのとき、サイズやフィットに関するデータがあることで、お客様がスムーズに商品を見つけ、安心して購入につながる。これは、今後の収益機会を広げるためにも非常に重要な要素になります。
まとめ:今こそ「サイズ課題」に取り組むべき理由
サイズやフィットに関する課題は、ファッションECにおける最大の障壁のひとつです。売上機会の損失、返品率の上昇、顧客満足度の低下など、さまざまな悪影響を及ぼしています。
こうした課題に対し、バーチャルフィッティングソリューションは明確な解決策を提示してくれます。購入率の向上、返品率の削減、そしてサステナビリティ目標への貢献——すべてを同時に実現できる可能性があります。
このテクノロジーはすでに実用段階にあり、十分な成果を出せる水準に達しています。AIやデータモデリングを活用した最新ツールでは、最小限の入力だけで高精度なサイズレコメンドが可能になっており、今まさに活用を検討する絶好のタイミングです。
ただし、成果を上げるためには、自社のブランドやビジネスニーズに本当に合ったソリューションを選ぶことが重要です。何を目指しているのか、どれだけのリソースを投下できるのか、そして何より「お客様が求めていることは何か」。こうした視点が欠かせません。
自社の課題とゴールに合致したソリューションを選定し、サイズ課題をビジネス成長の武器に変えましょう。
→ Under ArmourやAsicsの事例を見る(返品27%削減/ CVR10倍)
→ Virtusizeのデモをリクエストする(お問い合わせはこちら)

.svg)







.png)
